まだ若いころ、勉強を教えていて
「えっ?なんでこんな簡単なことが分からないのだろう?」
と思ったことは何度もありました。
でも、いまでは少々のことではビックリしません。
最近も、高校2年M君が、こんな式を書いています。
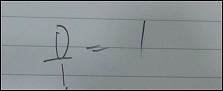
分数が苦手で、たとえば、「」 と 「
」 の違いについては、繰り返し説明をしてきたのですが、いまでも
になるときがあります。
正しい答になるその理由を説明すれば、ちゃんと理解できるのです。しかし、時間が経つと、「あれあれ? れれれ……」となってしまうのです。
数学全般に劣っているのではありません。定期テストではほぼ平均点。でも、分数は怪しいのです。
ごくごく希に、受け答えはまったくふつう他教科の成績は悪くないのに、算数・数学だけがどうしても成績が低迷する生徒さんがいます。
小島 寛之「数学でつまずくのはなぜか」(講談社現代新書)に「数を理解できない天才少女の話」として、こんなことが書かれています。ちょっと長い引用です。
(文中の遠山とは数学者で数学教育でも著名な遠山啓のことです)
....................引用..........................
数を理解できない天才少女の話
遠山の教え方のほうが、こどもたちに数というものを理解させやすいのは、事物が本来備え持ている「数」という属性を、うまく利用するからである。事物の側に 「 同数であることがわかる」という属性あり、こどもたちの側にその属性を受けとる感覚器が備わっている、それが数を理解できる原因なのだろう。だとすれば、これもまた一種のアフォーダンスである。
このことをより深く理解してもらうために 一つの実例を紹介しよう。それはサマンサ・アビールという学習障害者の話である。彼女は著書「13歳の冬、誰にも言えなかったこと ある学習障害の少女の手記』で、自分が数概念を認識できない障害を持ていること、そのためにどんなに苦しんだか、そしてその苦しみをどう克服したか、その体験を告白している。
この本は、「二十五歳なのに時計も読めないわたし、電話をかけるのも、お金の計算や小切手の収支合わせをするのもやっとなら、レストランでチップを払うのも、方向や距離感をつかむのも、毎日の生活で加減乗除の計算をするのも苦手」という衝撃的な言葉から始まる。
アビールは生まれついての学習障害を持っていた。それは、たぶん「数認識」にまつわるものだと思われる。数の大小や加減乗除がわからない。時計が読めない。お金の勘定ができない。また、単語のスペルを覚えるのも困難である。しかし彼女は知的障害者ではない。「数認識」以外は正常であり、むしろ普通の人より優れた才能を持ってさえいた。その証拠に彼女は、十五歳で最初の詩集を出版し、全米で話題を集め、賞を受賞し、各地で講演会を行っている。また、第二作にあたるこの『13歳の冬、誰にも言えなかったこと』は、現在の彼女の文章と少女時代の日記から成るが、どちらの文章も理路整然として論理的であり、文章を読む限り、そのような深刻な障害を負ているようには全く見えないのである。
彼女の体験は、人間の数認識の仕組みを知る上で、重要な手がかりを与えてくれる。
彼女の最初のトラブルは、小学校二年生のときに起きた。彼女はそれを以下のように書き記している。
それは、大きなロッキングチェアに腰掛け、腕を使って時計の形を作っている先生を囲んで座っていたときのことだ。先生は、両手を時計の針代わりにして、生徒たちに時計を読み取らせようとしたのである。ちょうど何時なのか、十五分過ぎなのか、三十分過なのかを答えさせようとしたわけだ。その授業では、頭が混乱して居心地が悪くなってしまったのを覚えている。先生の質問がさっぱりわからなかったからだ。
彼女は、時計が読めないことにこのとき気がつき、その後もずっと、そして大人になってさえも、読めないままである。興味深いのは、彼女は「数字を時刻に結びつけられない」だけでなく、「実際の時間の経過」もほとんど認識できない、という点である。そもそも「物理的な時間」を感受することできないのか、それとも記号で抽象化して受けとることができないことから「物理的な時間」をつかめないのか、それはこの本からは読み取ない。
彼女が数の計算の困難に直面したのは、同じ小学校二年生のときで、当時のことを次のように記述している。
母が最初に引いたカードは、「5-2=?」だった。わたしは、カードと赤い記号をじっと見た。「-」が引き算を意味していることは思い出したのだが、それ以外の意味はさっぱりわからなかった。頭の中は、真っ白になっていたのだ。わたしは一生懸命計算しようとしたが、空っぽのファイルキャビネットの中をさがし回っているような感じだった。
(中略)
「じゃあ、ここにカードは何枚ある?」
わたしはカードを数え上げ五枚」と答えた。
「正解。じゃあ、ここからカードを二枚取ったら、何枚残る?」
「えーと、三枚でしょ?」
混乱しながら、わたしはもう一度、そう答えた。正直言って、わたしには母の質問がまるでわからなかった。
(中略)
「5ー2は、3よ。いい、はじめにカーが五枚あってそこから二枚取ったから、残りは三枚になったの」
わたしはもう一度、母の顔をぽかんと見つめた。母の説明を聞いて 一生懸命わかろうとしたが、その言葉からは、意味がよるで読み取れなかった。論理の流れについていけなかったのだ。
ここには、「数え主義」や「集合算主義」を考える上で、とても象徴的なことがいくつも含まれている。まず、彼女は「数を唱えること」自体はできる、という点だ。彼女は、数を唱えることはできるが、しかし、「数とは何か」ということがまるでわかっていない。その感じが実にき活きと描写さている。
次に、母親はカードという具体物を使って、数とその引き算を教えようとしているのだが、彼女はカードから「数」という属性を抜き出すことがまるでできていない。彼女にはカードはカードでしかない。五枚と枚数を答えたときは、単に暗記している数詞を唱えただけなのである。その上、「カードを取り去る」ということを抽象化したものが「引き算」という演算である、ということが全く捉えられていない。
そして最後に、これが最も注目すべき点だが、この引用文は彼女本人の少女時代の日記であり、自分が「数を認識できない」という事実を、これほど的確にきわめて論理的に描写できている。つまり「メタ」のレベルでは、彼女は「数がわからない」ということがきちんと把握できてるのである。
もう一つ、彼女が、お金にまつわる認識ができないことを告白している部分を引用しよう。
これは高校生のときの日記である。
店員が「一五ドル二八セントです」と言ったので、財布を開いてみた。すると中には、二〇ドルが入ていた。それでは足りないかもしれないと思ったわたしは、時間かせぎに店員の言った値段をおうむ返しに繰り返した。
(中略)
わたしは財布を覗き込むと、一瞬ためらってから、二〇ドルを取り出した。その瞬間、心臓が止まった感じになった。音という音は、消え失せてしまった。店員に二〇ドル札を手渡し、その反応をじっと観察していたときは、すべての動きがスローモーションにでもなったかのようだった。二〇ドルでは足りないという暗黙のサインを読み取ろうとしていたのだ。
この記述でわかることは、彼女はお札に書いてある数字はわかるが、それを「金額」という数として認識ができず、だから大小を比較できない、ということだ。もっと正確に読解するなら、金額には大小があって、代金と同じかそれより多い金額を支払えばいいことは理解できている。しかし、そのことと、お札に書いてある数字とを結びつけることができないのである。
彼女のこの体験からわかるのは、「数がわかる、ということは、頭の良し悪じと直接関係するわけではない」ということである。彼女は優れた知性を持っているが、数認識のパーツだけが機能していない、そう考えるの正しいだろう。
この理屈を逆さまに用いるなら、こう言える。普通のこどもたちが数をわかることができるのは、「真白な頭」に教師によって上手に書き込まれたからでも、こどもたちが努力して理解したからでもなく、事物に備わる「数えられる」というアフォーダンスを受理する機能が、こどもたちに生まれつき備わっているからなのである。数は(アビールのような例外を除けば)はじめからこどもたちのなかにあるのだ。そして、それは事物の属性とて現れるのである。
............................引用終..............................
いままで、私が受け持った多くの生徒さんのなかで、アビールのような算数障害ではないかと思ったのはお一人だけです。
冒頭の簡単な分数をしょっちゅう間違える高校2年M君は、めんどだから思いつきで適当に答えているのであって、算数障害ではありません。
さて、最近の文科省の調査で、発達障害といわれる生徒の割合が、8.8%であることが明らかになりました。私は、発達障害と診断された生徒さんを、お一人長らく担当した経験がありますが、彼は数学Ⅱまで勉強できました。
発達障害だから数学ができないわけでもありません。また、算数障害だからといって知的な能力が劣っているわけでもありません。
○○障害と安易にレッテル張りをしてしまわず、どんな子にもその子にふさわしい伸ばし方がきっとあるはずだと思います。
